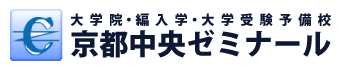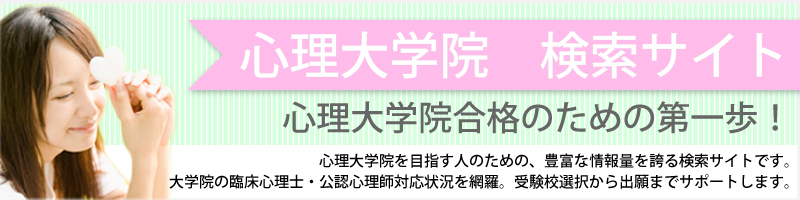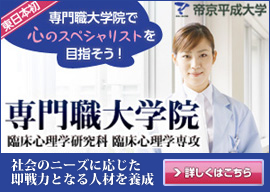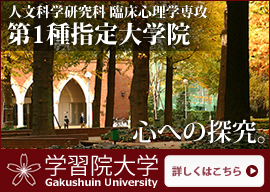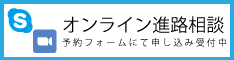- TOP
- 心理大学院検索
- 心理大学院入試日程検索
- 北海道医療大学大学院 心理科学研究科
私立
北海道 / 北海道
北海道医療大学大学院
心理科学研究科
臨床心理学専攻 臨床心理学領域
豊かな知性と感性で対処する 心の専門家を養成します。
| 臨床心理士 | 公認心理師 |
|---|---|
| 未指定 |

入試時期
年2回(9月、2月)
募集人数
第1回:15名以内(学内推薦、社会人を含む)第2回:5名以内(社会人含む)
出願期間
第1回:2025年8月25日(月)~9月8日(月) 必着
第2回:2026年1月13日(月)~1月27日(火) 必着
第2回:2026年1月13日(月)~1月27日(火) 必着
試験日
第1回:2025年9月18日(木)
第2回:2026年2月6日(金)
第2回:2026年2月6日(金)
試験科目
(1)専門科目
・臨床心理学および心理学
(2)外国語(英語)
・辞書使用可。ただし電子辞書は不可。
(3)面接
・臨床心理学および心理学
(2)外国語(英語)
・辞書使用可。ただし電子辞書は不可。
(3)面接
提出書類
卒業論文概要書、研究計画書
社会人入試
■出願資格
下記に該当し、実務経験5年以上あり、公認心理師法施行時点で継続している者。
(1) 大学卒業後、文部科学省令・厚生労働省令で定めた施設において、公認心理師法第2条第1項から第3項までの行為を業としていた者
■出願書類
研究計画書,履歴書,業務調書
■選抜方法
(1)小論文
・実務に関連したもの
(2)外国語(英語)
・辞書使用可。ただし電子辞書は不可。
(3)面接
・専門的知識に関する質問等を含む
下記に該当し、実務経験5年以上あり、公認心理師法施行時点で継続している者。
(1) 大学卒業後、文部科学省令・厚生労働省令で定めた施設において、公認心理師法第2条第1項から第3項までの行為を業としていた者
■出願書類
研究計画書,履歴書,業務調書
■選抜方法
(1)小論文
・実務に関連したもの
(2)外国語(英語)
・辞書使用可。ただし電子辞書は不可。
(3)面接
・専門的知識に関する質問等を含む
合格発表日
第1回:2025年9月25日(木)
第2回:2026年2月17日(火)
第2回:2026年2月17日(火)
入試説明会
大学院心理科学研究科 オンライン説明会を開催します。
北海道医療大学大学院心理科学研究科では、入試制度や心理実践実習、研究内容、就職などについての説明会を開催致します。
オンライン形式での開催です。是非ともご参加願います。
開催日時:2025年8月2日(土) 16:30~
事前申し込みは不要です。
https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/topics/information/1627865/
北海道医療大学大学院心理科学研究科では、入試制度や心理実践実習、研究内容、就職などについての説明会を開催致します。
オンライン形式での開催です。是非ともご参加願います。
開催日時:2025年8月2日(土) 16:30~
事前申し込みは不要です。
https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/topics/information/1627865/
研究室訪問
出願にあたっては、事前に研究指導を希望する教員に申し出てください
備考
※一般選抜の出願資格の1つに、次のものがある。
「大学において心理学を専攻し卒業した者」
「心理学・・・省令に定める『公認心理師関連科目』」
「大学において心理学を専攻し卒業した者」
「心理学・・・省令に定める『公認心理師関連科目』」
研究科の概要・特色
《日本初となる心理職の国家資格、公認心理師の資格取得に対応するカリキュラムへ》
心理職初の国家資格である公認心理師は特定分野での実習が必修となり、中でも医療機関での実習が必要となります。既に病院実習を取り入れ、附属病院を持つ本学ではこの強みを生かし、2018年度入学生より、今までの学びを発展させたカリキュラムを展開する予定です。
《独立した専攻としては日本初となる、言語聴覚学専攻を2006年4月に開設しました。》
実際の治療行為にも関わる言語聴覚士は、より高度な専門性、学問性が求められています。そうした社会的・学問的ニーズに応えるため、2006年4月、心理科学研究科言語聴覚学専攻を開設しました。2006年現在、言語聴覚学分野を設置している大学院は全国でわずか10校。独立した言語聴覚学専攻として大学院を設置するのは、本学が国内初となります。
心理職初の国家資格である公認心理師は特定分野での実習が必修となり、中でも医療機関での実習が必要となります。既に病院実習を取り入れ、附属病院を持つ本学ではこの強みを生かし、2018年度入学生より、今までの学びを発展させたカリキュラムを展開する予定です。
《独立した専攻としては日本初となる、言語聴覚学専攻を2006年4月に開設しました。》
実際の治療行為にも関わる言語聴覚士は、より高度な専門性、学問性が求められています。そうした社会的・学問的ニーズに応えるため、2006年4月、心理科学研究科言語聴覚学専攻を開設しました。2006年現在、言語聴覚学分野を設置している大学院は全国でわずか10校。独立した言語聴覚学専攻として大学院を設置するのは、本学が国内初となります。
求める人材
本学の教育理念である個体差健康科学に基づき、保健・医療・福祉・教育の領域における心理臨床の高度専門家および研究者として、または、高度な臨床能力と研究能力を持った言語聴覚士として、人類の幸福に貢献する志のある人材を求める。
心理臨床において、国際的水準で科学者の視点・実践家としての技能及び研究能力を兼ね備えた高度専門職業人として、幅広くこことの問題に向き合う志のある人材を求める。
心理臨床において、国際的水準で科学者の視点・実践家としての技能及び研究能力を兼ね備えた高度専門職業人として、幅広くこことの問題に向き合う志のある人材を求める。
担当教員
■教員名/専門
・冨家 直明 教授/臨床心理学、行動医学
行動医学的手法を用いた認知行動療法を専門に研究しています。広大な北海道の大地に認知行動療法の技法を普及、定着させるために、「誰でも使える化」を進めるべく鋭意努力中です。最近は、コミュニケーションスキル教育・メンタルヘルス教育をテーマにした映画撮影事業に取り組んだり、マンガを使ってPTSDの心理教育を実施できるようにしたりと、なるべく裾野を拡げていく方向に走っています。ゼミは学部3年生から修士課程までたくさんおります。教育機関はじめ地域のさまざまな施設と常に連携するように心がけています。防げるものは防ぐ。ならなくていい病気にはならない。当たり前のことがふつうにできるメンタルヘルス先進地域北海道を目指します。
・野田 昌道 教授/心理アセスメント(治療的アセスメント)、司法臨床
・森 伸幸 教授/認知心理学、認知行動療法
思考心理学(講義概要)
私たちは、日々の生活で実にさまざまな考えを頭の中でめぐらして行動している。そこに見られる法則や現象について実験的な事実をもとに講義をしてゆく。臨床心理学という分野においても、心理療法は、クライアントの問題解決を支援することであり、カウンセリングはクライエントにとって、そして同時にカウンセラーにとっても問題解決である。また、クライエントの思考のゆがみについてどのように考えたらよいであろうか。この講義では思考に関する基礎心理学的な知見を学習し、臨床的な応用を前提として,思考に理解を深める。
・百々 尚美 教授/生理心理学
生理心理学(講義概要)
本講義では、「脳と心の謎」について考えるために、中枢神経系、自律神経系、内分泌系、免疫系、骨格筋系、視覚-運動系についての生理心理学的知識を理解することを目的としている。
・今井 常晶 准教授/障害児心理学、音楽療法
発達障害児への発達支援の現場での臨床経験を踏まえ、臨床心理士・言語聴覚士・音楽療法士の3つの資格を取得する。
専門は発達障害児への音楽療法。
・金澤 潤一郎 准教授/心理学研究法
金澤ゼミでは,認知行動療法に基づいた基礎研究や実践研究を行います。卒業論文や修士論文のテーマは,発達障害特性をもつ大学生・高校生・子育て中の母親に関する研究,発達障害以外にも医療分野や司法分野など幅広く研究を行っています。また児童ディサービスや小学校など多くのボランティア活動,各種研究会や患者会への参加など,学外活動も積極的に行っています。
・本谷 亮 准教授/臨床心理学(認知行動療法)
専門分野は、臨床心理学(認知行動療法)、医療心理学、心身医学です。特に、慢性疼痛に対する心理学的メカニズムの解明や効果的な治療的アプローチの開発、効果的なリハビリテーションプログラムの開発と普及を研究テーマとしています。
ゼミでは、認知行動療法を基盤として、さまざまな不適応や諸問題を抱える方に対する援助方法を学び、考えます。特に、成人を対象とした医療領域での認知行動療法に関する諸理論と実践をテーマとして幅広く扱いますが、心身医学・行動医学関連のトピックも重視して取り上げます。ゼミを通して、上記テーマに関連した基礎知識や最新の知見を身につけるとともに、取り組むべき課題を探し、“臨床や現場に役立つ”ための研究が進められることを目指します。個々やグループで資料や論文を調べたり、まとめることもありますが、ゼミではワイワイとディスカッションしながら進めていきます。
机上の空論で終わらせないための”実践的な”学びを大事にしています。臨床心理学の奥深さ、心理療法の可能性を一緒に探求していきましょう。「なぜ、どうして」という単純な疑問、興味関心が何よりの原動力です。ワクワクする時間、ハッとする体験がゼミの中で共有できればと思っています。
・齋藤 恵一 講師/言語心理学
【教育方針】
単に事実を知ることよりも、どのようにしてそのような結論に至ったのかを理解することの方が大事ですし、そのようにして理解しようとする態度を持つことはもっと重要です。
・西郷 達雄 講師/臨床心理学(認知行動療法)
認知行動療法を基盤としてストレス関連疾患の発症および増悪メカニズムの解明と治療法について研究を行なっています。また、それ以外では医学教育(公認心理師養成)についての研究を行なっています。その中で、大学における修学不適応による休学および退学に関する調査研究を行なっています。心身および修学の不適応感は、休学あるいは退学の一要因となるため、早期発見・早期介入だけでなく全体に対する予防的アプローチが重要だと考えています。
・関口 真有 助教/臨床心理学(認知行動療法)
・冨家 直明 教授/臨床心理学、行動医学
行動医学的手法を用いた認知行動療法を専門に研究しています。広大な北海道の大地に認知行動療法の技法を普及、定着させるために、「誰でも使える化」を進めるべく鋭意努力中です。最近は、コミュニケーションスキル教育・メンタルヘルス教育をテーマにした映画撮影事業に取り組んだり、マンガを使ってPTSDの心理教育を実施できるようにしたりと、なるべく裾野を拡げていく方向に走っています。ゼミは学部3年生から修士課程までたくさんおります。教育機関はじめ地域のさまざまな施設と常に連携するように心がけています。防げるものは防ぐ。ならなくていい病気にはならない。当たり前のことがふつうにできるメンタルヘルス先進地域北海道を目指します。
・野田 昌道 教授/心理アセスメント(治療的アセスメント)、司法臨床
・森 伸幸 教授/認知心理学、認知行動療法
思考心理学(講義概要)
私たちは、日々の生活で実にさまざまな考えを頭の中でめぐらして行動している。そこに見られる法則や現象について実験的な事実をもとに講義をしてゆく。臨床心理学という分野においても、心理療法は、クライアントの問題解決を支援することであり、カウンセリングはクライエントにとって、そして同時にカウンセラーにとっても問題解決である。また、クライエントの思考のゆがみについてどのように考えたらよいであろうか。この講義では思考に関する基礎心理学的な知見を学習し、臨床的な応用を前提として,思考に理解を深める。
・百々 尚美 教授/生理心理学
生理心理学(講義概要)
本講義では、「脳と心の謎」について考えるために、中枢神経系、自律神経系、内分泌系、免疫系、骨格筋系、視覚-運動系についての生理心理学的知識を理解することを目的としている。
・今井 常晶 准教授/障害児心理学、音楽療法
発達障害児への発達支援の現場での臨床経験を踏まえ、臨床心理士・言語聴覚士・音楽療法士の3つの資格を取得する。
専門は発達障害児への音楽療法。
・金澤 潤一郎 准教授/心理学研究法
金澤ゼミでは,認知行動療法に基づいた基礎研究や実践研究を行います。卒業論文や修士論文のテーマは,発達障害特性をもつ大学生・高校生・子育て中の母親に関する研究,発達障害以外にも医療分野や司法分野など幅広く研究を行っています。また児童ディサービスや小学校など多くのボランティア活動,各種研究会や患者会への参加など,学外活動も積極的に行っています。
・本谷 亮 准教授/臨床心理学(認知行動療法)
専門分野は、臨床心理学(認知行動療法)、医療心理学、心身医学です。特に、慢性疼痛に対する心理学的メカニズムの解明や効果的な治療的アプローチの開発、効果的なリハビリテーションプログラムの開発と普及を研究テーマとしています。
ゼミでは、認知行動療法を基盤として、さまざまな不適応や諸問題を抱える方に対する援助方法を学び、考えます。特に、成人を対象とした医療領域での認知行動療法に関する諸理論と実践をテーマとして幅広く扱いますが、心身医学・行動医学関連のトピックも重視して取り上げます。ゼミを通して、上記テーマに関連した基礎知識や最新の知見を身につけるとともに、取り組むべき課題を探し、“臨床や現場に役立つ”ための研究が進められることを目指します。個々やグループで資料や論文を調べたり、まとめることもありますが、ゼミではワイワイとディスカッションしながら進めていきます。
机上の空論で終わらせないための”実践的な”学びを大事にしています。臨床心理学の奥深さ、心理療法の可能性を一緒に探求していきましょう。「なぜ、どうして」という単純な疑問、興味関心が何よりの原動力です。ワクワクする時間、ハッとする体験がゼミの中で共有できればと思っています。
・齋藤 恵一 講師/言語心理学
【教育方針】
単に事実を知ることよりも、どのようにしてそのような結論に至ったのかを理解することの方が大事ですし、そのようにして理解しようとする態度を持つことはもっと重要です。
・西郷 達雄 講師/臨床心理学(認知行動療法)
認知行動療法を基盤としてストレス関連疾患の発症および増悪メカニズムの解明と治療法について研究を行なっています。また、それ以外では医学教育(公認心理師養成)についての研究を行なっています。その中で、大学における修学不適応による休学および退学に関する調査研究を行なっています。心身および修学の不適応感は、休学あるいは退学の一要因となるため、早期発見・早期介入だけでなく全体に対する予防的アプローチが重要だと考えています。
・関口 真有 助教/臨床心理学(認知行動療法)
所在地・連絡先
〒002-8072
札幌市北区あいの里2条5丁目
入試広報課TEL:0133-23-1835
心理科学部代表TEL:011-778-8931
WEB:http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~koho/in_youkou/index.html