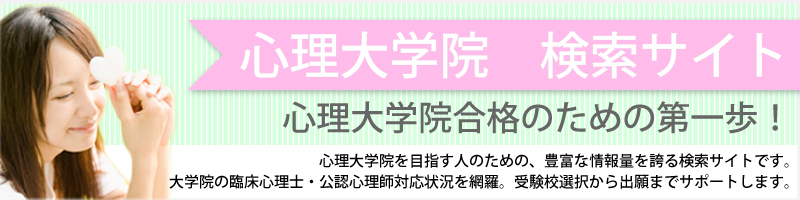
花園大学大学院
社会福祉学研究科
高い専門性と豊かな人間性を育てる
充実したカリキュラム
受験生へのアドバイス
学びたいという意欲を持って入学した社会人や留学生など、幅広い年齢層の多種多様な人々が、専門の研究を通して交流しており、お互いを刺激し高めあうことのできる理想的な学びの環境があなたを待っています。
入試時期
年2回(9月、3月)
募集人数
秋季:3名 春期:2名
出願期間
秋季:2025年9月5日(金)〜9月16日(火)
春季:2026年2月6日(金)〜2月16日(月)
試験日
秋季:2025年9月27日(土)
春季:2026年2月25日(水)
試験科目
英語(辞書持込可, 電子辞書不可)、専門科目、面接・口述試験
提出書類
研究テーマとその概要・研究計画書
合格発表日
秋季:2025年10月20日(金)
春季:2026年3月4日(水)
応募状況
■過去の入試結果
【2025年度】
秋季:志願者数4名、合格者数2名
春季:志願者数2名、合格者数1名
【2023年度】
秋季:志願者数1名、合格者数1名
春季:志願者数0名、合格者数0名
【2022年度】
秋季:志願者数7名、合格者数1名
春季:志願者数4名、合格者数3名
【平成29年度】
秋季:志願者数12名、受験者数12名、合格者数6名、入学者数4名
春季:志願者数 7名、受験者数 6名、合格者数1名、入学者数1名
【平成27年度】
秋季:志願者数8名、受験者数8名、合格者数3名、入学者数1名
春季:志願者数11名、受験者数9名、合格者数5名、入学者数5名
入試説明会
※大学院に特化した説明会は実施していません。
進路状況
備考
※臨床心理士養成は、2023年度入学生より停止します。
研究科の概要・特色
花園大学社会福祉学研究科(修士課程)は、1964年以来34年間の歴史をもつ学部教育の伝統に立って、1998(平成6)年に創設されました。
その後、学部に福祉心理学科(現、臨床心理学科)が設置されたことを受けて、2006年に社会福祉学研究科の中に臨床心理学領域が誕生しました。現在、社会福祉学研究科は社会福祉学領域と臨床心理学領域の2領域から成っています。
本学の特徴は、実践的で専門的な講義と現場経験が豊富なすぐれた教授陣にあります。また、1学年10名(2領域合わせて)という定員枠に演習担当教員が6名(各領域に3名ずつ)配置されており、他に類を見ない少人数教育を実現しています。
求める人材
・社会福祉法制、精神保健医療、児童福祉、家族福祉、NPO法・運営、福祉調査等の研究領域の基本的な知識を持ち、将来、福祉現場のリーダー、教員等の高度な専門性を要する職業等に従事する目的を持つ者。
・人と触れ合うのが好きで人に優しく、ヒューマン・ケアの仕事をするのにふさわしいパーソナリティの持ち主が望まれる。
・また「臨床心理士資格認定協会」より認定された、第一種指定校としてのカリキュラムに沿った教育及び実習を通して、現代の多様な心の問題の解決を支える臨床心理士を目指す者。さらに国家資格である公認心理師を目指す者。
担当教員
■教員名(専門分野)
*研究領域・テーマ
*研究者からのメッセージ
■渕上 康幸 教授(司法・犯罪心理学、心理的アセスメント)
*
応用心理学
少年非行のリスク因子の探求
素行症や反抗挑発症のサブタイプと併存症に関する心理学的研究
破壊的行動障害DBDマーチの実証的研究
ロールシャッハテストの量的検討
イレズミ,自傷行為がある者の心理的な特徴
*法務省の心理技官として,心理的アセスメントに携わるとともに,査定ツールの開発や素行症のリスク因子に関する実証的な研究にも取り組んできました。日本の殺人発生率が世界最小の理由は,少年非行が初期の段階で食い止められているためと考えられています。安心・安全な社会の実現には,早期発見と適切な介入が大切です。科学技術の進歩を活用し,そのための方法を考えていきたいと思っています。
■安田 誠人 教授(特別支援教育、障害児心理、重複障害児支援)
*
重度知的障害のある子どもに対する特別支援教育での支援の向上を目指して
インクルーシブ教育構築を目指しての就学支援のあり方に関する考察
ムスリム家庭の子どもに関する保育支援に関する研究
*障がいのある子どもに対する社会の理解は以前と比較するとかなり進んできています。特にインクルーシブ教育(特別支援教育)、合理的配慮、障害者の権利条約などの理念の広がりの影響が大きいと思われます。しかしまだまだ障がいのある子どもに対する差別、偏見は根強く残っているのも事実です。すべての子どもたちが生活しやすい環境を整えるために、福祉・教育・保育の立場で何ができるかをみなさんと一緒に考えていければと思っています。
■丹治 光浩 教授(臨床心理学)
*心理アセスメント全般
心理療法の技法的発展
*臨床心理学をベースとしながらも幅広い分野の研究から心の本質に迫りたいと考えています。
■村松 朋子 准教授(臨床心理学)
*心理アセスメント
心理療法
*適応能力を維持し、その能力を高める支持的精神療法や発達促進的アプローチをベースとした心理療法の実践的研究に取り組んでいます。中でも、心理アセスメントの新たな可能性を探求すべく、家族療法に家族アセスメントを組み込む実践研究を行っています。トラウマ・ケアにも取り組んでいます。
■妹尾 香織 准教授(社会心理学、臨床心理学、家族心理学)
*日常生活における退陣行動の効果・影響に関する実証的検討および夫婦や親子など現代社会における家族関係についての臨床・社会心理学的研究
* 今の一歩が次の世代の何かにつながることを信じて、研究、臨床、教育活動ともに日々努力していきたいと思います。 少しでも価値ある研究をして、一人でも多くの人と分かち合えたら嬉しいです。
■松河 理子 専任講師(臨床精神医学)
*精神疾患を抱える方の心理臨床
精神疾患の脳画像研究
女性のライフサイクルとメンタルヘルス
* 精神科専門医、臨床心理士。精神疾患のみならず、様々な理由で生きづらさを抱える人に寄り添っていけるような心理療法に関して興味を抱いてまいりました。今後は特に思春期・青年期の発達課題を中心に探っていきたいと考えています。
■岡 ひろみ 講師(教育学 社会学 特別支援教育)
*特別支援学校における「音楽づくり」の実践的意義と可能性
特別支援学校における不登校生徒の現状と支援体制、外部機関との連携のあり方
*特別支援学校では、授業を創意工夫する楽しさを感じ、支援が必要な子ども達の生き生きとした姿に接してきました。
現場での経験を生かして、具体的な教材や映像やエピソードを交えた講義を行います。医療・福祉・行政との連携の必要性や子ども達や保護者の願いなど、特別支援教育の魅力を感じてもらえると嬉しいです。
■川島 民子 専任講師(特別支援教育、発達性協調運動障害、キャリア教育)
*発達性協調運動障害の児童生徒に対する実践のあり方
知的障害の児童生徒に対するキャリア教育の在り方
通常の学校における特別支援教育の専門性の向上に係る研修のあり方
*特別支援学校で多くの子どもたちと保護者に出会い、たくさんのことを学ばせてもらいました。一人ひとりの子どもたちはそれぞれの可能性をもっています。その可能性に目を向けながら一緒に進んでいく楽しさを感じてもらいたいと思います。
学内での学びとともに、実際の現場にも足を運ぶことを通して、特別支援教育の奥深さを学んでいきましょう。
■角谷 基文 専任講師(実験心理学、社会脳科学、発達心理学)
*他者との関わりの計算・脳基盤に関する研究
自閉スペクトラム症者の社会的動機づけに関する量的・質的研究
*人々はコミュニケーションの中で何を感じているのか?私はこの問いを自身の研究テーマとし、質問紙法や心理実験、質的研究以外にも、脳機能イメージングや計算行動科学など多様な手法を用いて探求しています。
■谷田 勇樹 専任講師 (認知心理学、認知科学)
*記憶メカニズムと言語構造の関係
*私達は言語を扱うことができます。しかしよく考えてみると、それは当たり前のことではないように思います。たとえば単語の数は膨大です。我々はこんなに多くの単語をなぜ記憶し、扱えるのでしょうか?私はこの問いへの答えとして、言語そのものが人間にとって記憶しやすくなるように構造化されているからだと考えています。この仮説を検討するため、私の研究では記憶の仕組みを解明する実験や、言語の構造を解明するテキスト解析を行っています。
キーワード
ページトップへ