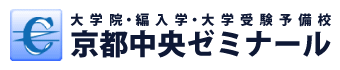○京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻
専門科目
【傾向】例年、大問2問から構成され、(1)語句説明問題、その語句と関連する用語の選択問題と、(2)主に臨床心理に関連する文章を読んで、穴埋めや、文章の要約を踏まえた短い記述問題が出題される。年によって差があるが、難解な問題が出題されることがあり十分な準備が必要である。
(1)は、10個の語句の説明と、それぞれに対応する関連用語の選択が求められる。内容は、基本的な語句に加えて、難解なレベルの語句も出題される。範囲は、心理学全般からの出題で、基礎心理学(学習・記憶・知覚・欲求など)、発達心理学、社会心理学、心理統計学、および臨床心理学(心理検査・心理療法・異常心理学・地域援助など)などから出題されている。特に臨床心理学からの出題は多く、力動心理学の深い知識を問われることが多い。また研究倫理を問われた年もある。
(2)は、臨床心理学に関連する有名著者の著作等から抜粋・編集した形で文章が提示され、文章中のくり抜き部分に当てはまる語句の選択、記述が求められることが多い。また、文章を踏まえた問いが設定され、50字前後で簡潔に説明することが求められる。
内容は、心理面接の基本的な事項、力動心理学に関する重要概念を中心に出題されるが、発達臨床、心理査定の深い知識を問われた年もある。選択式の穴埋めは、取捨が難しい選択肢が一部混ざっており、慎重な対応が求められる。説明問題は、単純に知識を披露するのでなく、文章内容を踏まえたうえでの回答が求められる。字数が短い文、的を得た回答が求められる。
【対策】(1)に対しては、簡潔に定義を説明することが求められる。学習で学んだ用語をノートに簡潔にまとめるなど、学んだ知識をアウトプットする練習が欠かせない。
心理学全般の知識を理解したうえで、臨床心理学、特に力動心理学については深く掘り下げて理解していくことが求められる。力動心理学の理解には、時間が掛かる。その部分を掘り下げすぎて、基本的な知識をしっかり身に着けることをおろそかにしないように学習を進めることが大切である。
(2)の鉄則は、文章をしっかり読む、文脈をしっかり押さえるなど、現代国語の読解スキルを十分発揮し、文章を要約して対応することである。これだけで、選択肢の消去が可能な面が大いにある。単純に知識に頼って問題を埋めていくのは危険であり、しっかりと読み込む練習が欠かせない。
年度によって差があるが、臨床心理面接、臨床心理査定の深い理解を問われることが多い。過去問で出題された著作を読み、その考えを要約するなど、臨床感を深めると同時に、アウトプットする訓練が大切である。加えて関連する論述の演習問題に取り組み、自分の考えをまとめる練習を進めることが重要である。