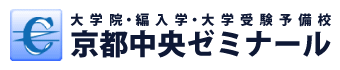先日実施された「北海道大学法学部編入学試験」
中央ゼミ生が受験した本年度の問題を英語担当講師に
解説解答を作成してもらいました。その一部を公開します。
参考にしてみてください。
平成26年度 北海道大学法学部編入学試験 英語 解答案・解説
問題1
【問題1総評】
問題文は、言語学、なかでも複合語(compound; 複数のパーツから作られる単語)の形成を題材としたものである。言語についての親しみがない受験生には、少しとっつきにくいテーマだったかもしれない。
言語の歴史をひもといていくと、現在ヨーロッパやインドで話されている言語は、いわば「親戚どうし」の関係にあることが分かっている。そのような言語を総称して「印欧(インド・ヨーロッパ)語族」と呼ぶが、この語族に属する言語の「共通の祖先」が印欧祖語(Proto-Indo-European language; 問題文に付されている訳注は若干不正確)と呼ばれている。
(1)
複合語をもつ言語においても、複合語のすべてが同じ方法で形成されるわけではない。
【解説】
those = languages; them = compound words.
(2)
もともとの印欧語では、この種の複合語で前に置かれる接辞は、厳密にいえば、「語」ではなく語基だったのだ。語基というのはすなわち、それが文中で単独で現れた時にはもつであろう、格・数・文法的性・叙法・時制・人称などの文法的特性を欠く語のことである。
【解説】
ここにも言語学の専門用語が何個か使われている。Prefixは動詞としても名詞としても使われ、たとえばadequate「適切な」に否定を表すパーツであるin- が付くとinadequate「不適切な」という語になる。このようにして何かの語に前から別のパーツをつけること、また、そうして付けられるパーツ自体のことをprefixと呼ぶ。
Grammatical featureの例として挙げられている概念のなかにも、英語以外の外国語の学習経験がないと理解しにくいものがあった。Case(主格、目的格などの「格」)、number(単数、複数の「数」)、gender(文法的性。たとえばドイツ語には「男性名詞」「女性名詞」「中性名詞」がある。基本的には生物学的な性別とはまったく関係しない)、mood(直説法、仮定法などの叙法)、tense(現在過去の時制)、person(一人称、二人称の「人称」)などである。これらの専門用語は外国語の学習経験から想像がついて訳せればラッキーであるが、できなくても必ずしも大勢には影響ないだろう。
(3)
この2語のうち前者は、どんな格ででも、まだ、どんな数ででも、そこに現れることができる。そして、複合語の意味は、それに応じて変わってくる。
【解説】
Varies(原形: vary)が一見したところだと動詞っぽく感じられないが、andのあとの節のメインの動詞として使われていることに注意。
(以下省略)
中央ゼミ生徒には、問題1・2とも全問解答解説を無料で配布しています。
ご希望の方はお申し出てください。