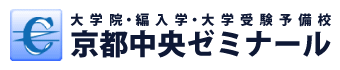物性薬学
クロマトグラフィー、滴定実験が頻出です。クロマトグラフィーの種類と原理、特徴をまとめておきましょう。理論段数などやや専門的な内容も出題されます。中和滴定、酸化還元滴定もよく出題されます。反応自体は典型的なもので高校化学の理論が理解できていれば十分解答できますが、本試験の特徴としてファクターを計算させることが多いです。ファクター計算は難しいものではありませんが、高校化学では扱われないものなので注意してください。
生命薬学
出題範囲が広く、傾向が不安定です。エッセンシャル分子生物学のような分子生物の教科書を一通り読むことをお勧めします。生理学についても簡単な本を読んで知識をつけておくとよいです。生命科学がほとんど初学の場合、まずは高校生物の「体内の恒常性」の分野を勉強してみましょう。アミノ酸は略式名、特徴(液性、親水度など)細かく覚えましょう。できれば構造式も書けると望ましいです。
分子薬学
出題は大学の有機化学が中心になります。構造の穴埋め問題、フィッシャー投影式で構造が表わされている出題が目立ちます。一部、非常に高度な問題がありますが合否を分けるような問題ではないので捨ててしまって問題ないでしょう。教科書に書いてある典型的な反応は電子の動きも書けるようにしておきましょう。教科書は、マクマリー有機化学(上中下)、ボルハルトショアー(上下)あたりが出題の難易度的にお薦めです。短時間で有機化学を仕上げたい方は「マクマリー概説」を読んでみるのも手です。