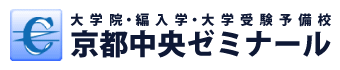今回は歴史学における年代の決定について書いてみようと思います。歴史は過去の出来事を扱う学問なので、ある事件がいつ起こったのか、ということが重要な意味を持ってきます。事件の目撃者が記録を残していて、そこにいつ起こったのかはっきり書かれていれば問題はないのですが、古い出来事になるとそういう記録が残っていない場合が多々あります。
例えば、かつてヨーロッパでは聖書に書いてあることはすべて事実であると信じられていました。神の天地創造やノアの洪水など、聖書に記されている様々な出来事は、多くの場合、それがいつ起きたことなのか明確に示されていません。さて、大航海時代以降ヨーロッパ以外の地域についての知識が増えてくると、エジプト、インド、中国などの歴史の古さがヨーロッパでも認識されるようになり、聖書の出来事の年代を確定し、天地創造がそれらの国の歴史より前に起こったことを示すことで、聖書とキリスト教の教えの正しさを証明する必要性が出てきます。そこで、16世紀ころから18世紀半ばころまで、聖書の年代についての研究が様々な学者たちによって行われました。万有力学の法則で有名なニュートンも聖書の年代決定に熱中した1人です。また、『ローマ帝国衰亡史』の著者エドワード・ギボンもその自伝の中で、一時期この問題に熱中し、眠れない夜を過ごしたと述べています。彼らの努力や成果が、現代の歴史学において顧みられることはほとんどありません。しかし、様々な史料を比較照合して特定の出来事の年代を推測する研究方法の礎が築かれ、普及浸透したのは彼らのおかげでもあり、現代の歴史学はこういった忘れられた多くの先達に支えられているのです。
疋田先生