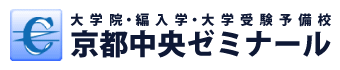スタッフの三戸です。
過去問整理も仕事の一つです。
実際に受験した生徒から譲り受けたり、
大学に問い合わせをしたりして手に入れた過去問を、
一つ一つファイリングして授業やCoZで使えるようにしています。
その作業の中で問題をチラチラ見たりはするのですが、
専門性の高い問題は、ちんぷんかんぷんを通り越して、
もはやてぃんぴゅんきゃんぴゅんなので、
これが分かる人には分かるんだなあと思いながら整理しています。
ちなみに、私は7年間大学で国語学や国文学を学んだ身ではありますが、
国文学系への編入試験や院試の問題もちんぷんかんぷんです。
私の7年間は一体なんだったんだろうという気分になります・・・
そんな私でもなんとか太刀打ちできそうなのが小論文系の試験。
面白そうな問題があると、
自分ならどういう回答をするかとついつい考えてしまいます。
その中でも特に面白そうだと感じたのが、
どこの大学の問題だったかは忘れましたが、
楽○やファースト○テイリングなどの企業が、社内公用語を英語にしていますが、あなたはそのことについてどう考えますか。良い点と悪い点を挙げて論じなさい。
といった問題。
企業だけではなく、山梨大学が講義をほぼ全て英語化すると発表したり、
幼少時から英語教育をする保育園が人気であったり、
何かと英語がもてはやされている昨今ですが、
私は大学で国語学を勉強していたためので、
ほとんど英語の勉強をしておらず英語が苦手な
国語<英語
な風潮は気に入りません。
確かに、「グローバル化」という言葉が声高に叫ばれるようになり、
それにつれて英語教育の重要性が説かれるようになって久しいですが、
果たして「英語を話す=グローバル」なのでしょうか?
私はそれは違うと思います。
確かに、「英語を話せると十億人と話せる」という
英会話学校のキャッチコピーにもあったように、
多くの人と話すことができるようになる、というのは利点でしょう。
しかし、英語が話せたところで、それで自分の主義主張を伝えなければ無意味です。
もし(またドラえもんネタですが)「ほんやくコンニャク」ができて、
言葉の垣根がなくなったりしたら、
そのとき、英語を話すことのどこにグローバル化の要素があるでしょうか。
結局のところ、「グローバル化」に必要な能力は、
「人と話す能力」ではなく「人に伝える能力」だと私は思います。
きっと、お上の役人は得意げに小学校から英語を必修化して、
「これで我が国もグローバル化できる」とか考えているのでしょうが、
全くの見当違いです。
国語に対する蔑視は、ともすれば愛国心の希薄化に繋がるとも思います。
行き過ぎた愛国心は全体主義に繋がりかねないので有りすぎても困りますが、
なさすぎるのもこのグローバル社会では致命的ではないでしょうか。
日本人としてのアイデンティティーがあってこそのグローバリズム、私はそう思います。
そういった意味では、公○式のCMは私にとっては好感触です。
英語教育のCMもしてますが、国語の重要性を説くCMもしています。
ただ、キャッチコピーの
く○ん、いくも○
は、「く○ん」と「いくも○」の間に
「に」や「へ」と言った助詞が省略されていて、
綺麗な国語とは言い難いのでいただけません。
会社全体のキャッチコピーなので仕方ない部分もあるでしょうが、
国語教育を謳うならそこは徹底してほしいところです。
ちなみに私には英語どころか日本語もまだ喋れない赤ちゃんがいますが、
国語を学んだ者として、きちんと国語を教えていきたいと考えています。
…と言いつつ子どもにN○Kの子ども向け英語番組を見せてたりするんですけどね。
大事なのは、国語をないがしろにせず英語も学ぶ、ということで。
英語だけに限らず他の科目にしても、論文を書くにしても、
口述試験を受けるにしても、国語力は必要ですからね。
「国語は全ての学問に通ず」です。
あ、当然ですが、
受験では英語を軽んじてはいけませんよ。
特に編入学や大学院入試を目指す人は取りこぼしは許されません。
専門性の高いこれらの試験では、
英語を学ぶことが専門科目を学ぶことにもなり、
専門科目を学ぶことが英語にも繋がります。
バランス良く勉強していってください。