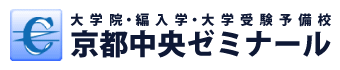法科大学院に入学するためには、未修・既修を問わず、適性試験を受験し、高得点をあげることが必要になります。特に未修コースの場合、適性試験の成績が数少ない客観的な資料となるので、高得点を取る必要性が高いです。
適性試験には、大学入試センターが実施する「法科大学院適性試験」(以下「センター」といいます。)日弁連法務研究財団が実施する「法科大学院統一適性試験」(以下「日弁連」といいます。)の2種類があります。
両者とも、推論分析分野と文章読解分野があります。文章読解分野については、大学入試までの国語の問題とほぼ同じなので過去問をとくことで十分対応できると思います。(もし、苦手な場合には、センターの場合は大学受験のセンター試験の現代文の参考書を、日弁連の場合には公務員試験の文章理解の参考書などで対策をすればよいでしょう。)
次に、推論分析分野について説明します。推論分析分野とは、中学入試の算数に出題されそうなパズルのような問題が出題される分野をいいます。そして、センター・日弁連ともに、同じ適性試験という名称であり、事務処理能力・思考力を問う点では同じですが、異なる点があります。すなわち、センター試験の場合は、年度によって若干の変化があるものの、未知の問題を問題文に書かれている条件・誘導を参考にして処理することを要求しています。他方、日弁連の場合にはある程度パターンがある問題をとにかく素早く解くことを要求しています。このことからその対策方法も若干異なることになります。
具体的には、センターの場合はまず、必ず「時間をはかって」過去問を解くことから始めます(これは両者とも共通です)。そして、センターの場合にはこの問題はどのようなことを聞いている問題なのかと言ったことを念頭におきつつ検討をします。具体的には、自分はこういう解き方で解いたけれども、これでは時間がかかりすぎるからどのようにして解けばよかったのか、問題文のこの条件はこのようにして使うのか、ここがわからなかったから解けなかったのかなどを考えるということです。(この他に、練習問題として国家公務員Ⅰ種試験の過去問もよいでしょう。)
他方、日弁連の場合には、まずは、『上・中級公務員 標準判断推理―確かな解答力が身につく“基本書” 』(田辺 勉・実務教育出版)などで基本的な問題のパターンを学びます。そのうえで、過去問を「時間をはかって」解き、素早く解く練習をするとよいでしょう。
なお、大学受験や、公務員試験の参考書をあげましたが、これらの参考書の全てが適性試験に必要なものとは必ずしも限りません。過去問を参考に、必要な部分をピックアップしていけば十分でしょう。
武田先生