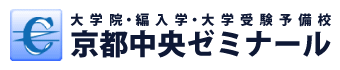大学院入試に出てくる英単語のレベルはとても高く、どの受験者でも(教えている我々でも)知らない単語が必ず出てきます。その際、そうした未知の単語のさばき方を日々、訓練しておくと、本番で必ずや役に立つと思います。以下、未知の単語のさばき方を紹介していきます。
- 品詞の判別
未知の単語の意味を類推する際、何よりもまず品詞の判別をすることが重要です。特に、名詞・動詞・形容詞・副詞の品詞判別をしっかりと行います。というのは、文の構造を決定する上でこれらの品詞は決定的に重要で、かつ、接続詞、関係詞、疑問詞などと違い、数が桁違いに多く、類推せざるを得ないものだからです。
- 形容詞
形容詞は同じ意味、あるいは同系列の意味の語を並列にすることが(特に名詞を修飾する際に)しばしばあります。その際、一方だけを訳しても十分に意味が通じる日本語になります。というのは、日本語にはそうした英語の表現方法があまりないからです。したがって、形容詞が並列になっていて、一方の単語が分からない場合、分かる方の単語の意味だけを訳す、ということで対処できます。
- 名詞
名詞は、その名詞がどういったグループに属しているかを類推できるケースがあります。例えば、動物名、疾患名、臓器名、国名といったグループです。グルーピングが出来れば、下線部和訳になっていない場合、読み飛ばすことができます。また、名詞を文脈から意味を類推できない場合、「もの」「こと」という訳を当てて対処できることもしばしばあります。
- 副詞
未知の副詞は文脈に沿う意味を推測するか、「とても」「ひどく」という訳を疑ってみる。それでも文として意味が通じない訳しか思いつかない場合、無理に意味の通じない日本語になるくらいなら、敢えて訳さない。
次回は、動詞のさばき方を紹介します。
小見先生