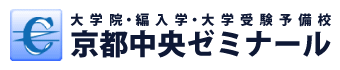人は、人生の様々な場面で、主体的に自らの行いを為すことを求められます。自分自身の行為の主体として、その行為に責任をもつことは、人が人として生きていく上で外すことのできない制約の一つではないかと思います。この制約は、足枷として行為を制限すると同時に、行いの指針として行為を衝き動かすものともなります。それゆえ、主体的に行為することは、人生を左右する重要な要因となり得ます。それでは、人はいかにして主体的に行為することができるのでしょうか。
ドイツの哲学者J.G.フィヒテは、人が主体的に行為するには、その行為の意識が必要であるとします。たとえば、「水を飲む」という特定の行いを為す人間は、自分が水を飲もうとすることと自分が水を飲んだこととを意識しています。人は自らの行為を何らかの仕方で常に意識しているものです。それゆえ、自らの行為の意識がなければ、人は行為主体ではなくなり、単に運動するものであることになってしまいます。
さらにフィヒテによると、その行為の意識には「考える」という働きが密接にかかわっています。たとえば、自分が水を飲むことを意識することができるのは、それを飲むのが他人ではなく自分であること、それがお茶ではなく水であること、さらにはそれを捨てるのではなく飲むことを「考える」ということ介してのみです。自分が水を飲むことは、それ以外の可能性(例えば自分が水を捨てる、あるいは、自分がお茶を飲む、等々の可能性)を常に考えていなければ、明瞭に意識されることはありません。このように、他の可能性を「考える」という働きがあることによって、行為は明瞭に意識され、人は自らの行為の主体となることができます。「自分が水を飲む」ということが、それ以外の行為の可能性を考えることにおいて明瞭に意識されてはじめて、人はその行いを自らが為していることとして引き受け、その行為の主体となることができるのです。
このように、主体的に行いを為すには、その行い以外の可能性を考えることが最も重要なことであると言えます。さまざまな行いの可能性を考えることにおいてはじめて、自らの行いを為すための指針が現れてきます。さまざまな可能性の中から大学院入学や、大学編入を選択するという新たな行いを為した皆さんの内には、その指針が既に現れているのではないかと思います。その指針こそが、皆さんが自らの行為によって最初に手にしているものです。手にした指針を信じて、自らの行為を最後まで続けてみてください。
古川先生