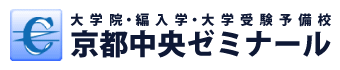就職活動や大学院の面接で頻繁に(ほぼ必ず?) 聞かれる質問として、「あなたはなぜそれをやろうとしたのですか?」という問いがあります。面接官としてはその人がどのような目的を持って行動していたかを見ようとしているようですが、目的のない「なんとなく」の行動は面接などのオフィシャルな場では評価されないと言われています。
私は大学時代法律を勉強していたのですが、法律の1つ1つの条文もただ「なんとなく」あるのではなく、全てに趣旨や目的がありました。これは、法律の運用は、お上が決めたルールを強制するものですから、当然の配慮です。そして、期末試験で、その条文の解釈で迷ったときでも、その趣旨や目的に立ち返れば、案外すんなり問題が解けたりしました。例えば、「民法94条2項の趣旨は、虚偽の概観を信頼した第三者を保護する趣旨であるのが、この場合は~なのでそれを類推適用することはできない」などです。
皆さんは、勉強をしていて何のためにこんなことをしているのか分からなくなることもあるかもしれません。そんなとき、「アフリカには勉強したくてもできない人がいるのに、お前は恵まれている。だから頑張れ!」という人もいますが、京都に住む一般人の想像力がアフリカの子供まで及ばないのは普通でしょう。もうすこし身近な視点から、自分は何のために勉強しているのかということを問いかけるのが一番だと思います。
勉強を始めるにいたった、最初の動機は「偉くなりたい」でも、「金持ちになりたい」でも、それ自体はその人の価値観なので何でもいいと思います。しかし、そればかりだと、面接がありうる大学院入試では、面接官に見抜かれて苦労することにもなりかねません。そうした勉強を継続することにおける「理念」は、ただガリガリ勉強するだけでは得ることはできないので、専門書以外の本を読んだり、ボランティアなどの課外活動も並行する必要があるかもしれません。
偉そうなことを書いてきましたが、私自身も実はこの講師の仕事を、当初は「お金を得るため」に始めました。しかし、今後のためにも、仕事を進めるに当たっての理念といったようなものを大切にしたいと考えています。その1つの候補として、私は中高6年間、中央ゼミナールのような個別指導の塾に通っていて、そこで学力が飛躍的に伸びたので、今度は講師として業界に恩返しがしたいというものがあります。
そういうわけで、「業界への恩返し」という理念をもとに精いっぱい頑張っています。
宍戸先生
Iconic One Theme | Powered by Wordpress