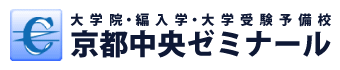京都大学経済学部第三年次編入学試験では、経済学試験と語学試験の2つがある。以下では、もっぱら経済学試験について述べる。
経済学試験では、いうまでもなく、経済学の問題が出題される。平成28年度編入学試験ではこれまで通りミクロ経済学1問、マクロ経済学1問、社会経済学2問から2問を選択して解答することが求められている。
これら4問のうち、いずれを選択するべきか。多くの方が前二者を選択するだろうから、翻って今回は後者の立場から編入学試験を紐解く。
今日、ほとんどの大学の経済学部で教えられている経済学は、ミクロ経済学とマクロ経済学である。そのため、ほとんどの学生がミクロ経済学とマクロ経済学の問題を選択することになる。それはそれで問題ないのだが、せっかく京都大学の経済学部に入るのなら、この際、社会経済学を学んでみるのも悪くない。なぜなら、今日、社会経済学を学べる経済学部は京都大学以外にほとんどないからである。
とはいえ、入学試験はあくまで大学に入るための手段にすぎないのだから、自分が得意な問題を選択すればよい。ただ、とりわけミクロ経済学の問題は、ほとんどが計算問題であり、数学が得意な人ならそれほど問題ではないが、そうでない人には難しく感じられるかもしれない。それに対して、社会経済学の問題は、計算問題も出ないことはないが、ほとんどの問題は論述式であり、きちんと対策さえしておけば、数学がそれほど得意でない人でも十分解答することができる。最近では、社会経済学の教科書もたくさん出版されてきているので、試験対策もしやすくなっている。
京都大学経済学部第三年次編入学試験を考えている人は、その点を考慮して、経済学試験に備えよう。
※平成29年度編入学試験からの変更点
平成29年度第三年次編入学試験からはこれまでとは異なる選抜方法がとられる。専門科目ではミクロ経済学1問、マクロ経済学1問、社会経済学1問より2問を選択して解答する。また、英独仏語学の筆記試験は廃止され、一次選考として成績証明書およびTOEFLの試験成績により選抜が実施されることとなる。
加藤先生