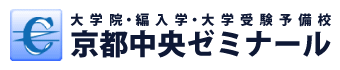京都、最後の村-南山城村に童仙房という集落がある。京都市内から電車を乗り継いで約二時間、大河原駅から車で山に登る。急な斜面を登りつめると目前に広がる、茶畑の連なった村の風景はジブリの舞台にでもなりそうな緑と清水の美しいところである。しかし、他の農村と同じようにこの集落でも人が減り続け、五年ほど前に小学校が廃校になった。地域の未来を危惧した村人が京都大学に相談を持ちかけたのをきっかけに、地域と大学が連携して定期的に活動・研究を展開している。
このたびの震災で私たちは先人の経験知を受け継ぐことや地域のつながりの大切さを思い知らされ、助けあうネットワークづくりや防災教育への関心も高まっている。生涯教育の研究・実践の領域でも「災害」という視点から日々の暮らしや、学びあう共同体としての地域のあり方を見直す取り組みを始めている。その第一歩として、童仙房で地域防災ワークショップを行い、昭和28年の南山城大水害を経験した方々とその時の記憶を語り合う場を持った。防災を入口にして語り合ううちに、地域の持つ課題や弱みが明らかになると共に、山間部の暮らしの自助に優れた側面の魅力も再認識された。そして何よりも、実際に災害を経験した人の記憶…音や光、そして情感豊かな語りを共有することで、災害という非日常へ向きあう心の準備ができたように思う。
鎹先生