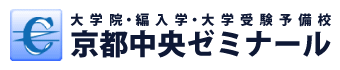現代の社会では様々な仕事が専門職化されている。「医師」、「看護師」、「教師」、などの固有な資格や専門性を持った人々が、それぞれの場所で、そしてそれぞれの場面で各々の専門性を生かして仕事をしている。私たちはこれらの仕事の専門性を当然のこととして受け止めがちであるし、それぞれの職種がそれぞれの領分を侵すことなく、矛盾なく仕事をしていくことを期待する。
しかし、現実の生活で出くわす問題の多くが、実は複数の領域にまたがる複雑な問題である。例えば、家庭におけるネグレクトの問題は、多くの場合、単に親の人道的な問題と言うよりも、心理的な困難や経済的な逼迫、社会的な孤立を背景としている。このような場合は、医療の専門家、福祉の専門家、学校の教師、地域のコミュニティなどの様々な専門家集団、もしくは組織が協働して子どもと家族を援助していく必要がある。その折には、異なる業種間での円滑なコミュニケーションや関わるタイミングの調整などが課題となり、「専門家」は職種の境界を越えて協働していくための意識を育て、自らの経験や専門性に基づく知を共有知として生かし合うことを考えなければならない。
今後、貧困などの社会問題だけでなく、さまざまな場面で、「領域を超える」ことの大切さが実感される場面が増えるかもしれない。高度な技術を持つ科学者は、その技術をどう使うべきかを社会と照らして考えていく上で、他の領域の研究者と協働する必要があるかもしれないし、経済的な開発を推し進めようとする事業家は、その地域の文化や自然を知らなければ、大変な過ちをおかしてしまうかもしれない。これからの「働くひと」は、多角的な視点から、よりよい仕事の「場」を創りだすために、自分の専門分野を超えて、いろいろな世界に目を向け、他者と理解し合う姿勢を育てることで仕事の可能性を広げていけるのではないかと思う。
鎹先生