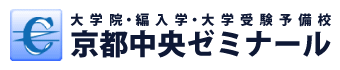昨年末、地元で同窓会があり6年ぶりに高校時代の仲間が集まった。私は大学で日々研究に携わる生活を送っているが、久しぶりに再会した友人たちの多くは一般企業で働いており、普段聞けない様々な話を聞けた。その中で印象に残っている話を一つ紹介したいと思う。
大学で理系学部に所属すると、おそらく多くの人がプログラミング言語を学ぶ。プログラミング言語はコンピュータに命令をする際必要になるもので、多くの工学機器には必ず使われている。話をしてくれた友人は銀行に就職し、システム管理を行っているそうだが、そこでも勿論プログラミング言語は使われている。コンピュータはプログラム通りにしか動かないのでたまに些細なミスで管理しているサーバがダウンすることがあるらしい。非常に複雑なプログラムであるためだろうと納得しそうになったが、原因を聞いて驚いた。それらの事故の多くは、ヒューマンエラーにより起こったようで、しかもとても簡単なミスということだった。分かりやすく言うと、例えば、数学の問題を解く際、「ただし正の整数とする」といったような基本的な条件文を書き忘れたと言ったような内容である。身の回りのプログラムで制御させた機器はとても複雑に見えるが、実は、基礎が積み重なってできたものだと改めて気付いたと同時に、高校や大学の数学で嫌になるほど指摘された条件文の重要性を今知ることになった。ものごとを始める時、初めは基礎ばかりが続き退屈だが、それが一番重要だということだろう。
甲斐先生