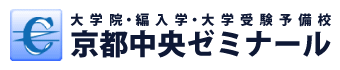皆さん、あけましておめでとうございます。数学講師の舩橋です。
今回は、私の実体験に基づく数学の勉強法について書きます。数学の問題を解く時は様々な試行錯誤を行って泥臭く問題を解いていきます。問題をみて試行錯誤を行えるだけの基礎力と、試行錯誤の中で正しい道筋を見つけられる応用力を身につけましょう。
数学の問題を解くというのは、クロスワードや数独などのパズルを解くのと非常によく似ています。なぜなら、
1.正しいか分からないけれど、分かることを試してみる:試行錯誤パート
2.試してみた中で、正しいものを選んでいき、完成に至る:応用パート
という流れで共通しているからです。解答用紙も計算用紙も白紙のまま、「分からなかった」と諦めることのよくある方、どんな些細な思いつきでも連想でも構わないので、自信を持って、とにかく書いて試してみましょう。ひょっとしたらその方向で問題が解けるかもしれませんし(数学の問題の解き方は1通りとは限りません)、少しでも答案に記述があれば部分点が貰えるかもしれません。クロスワードを解く時を思い出して下さい。何か書きこんでおけばそれがヒントになって他の問題も連鎖的に解けたりするものです。なにも書きこまなければそれより先に進むことはあり得ません。
さて、このような問題の解き方を踏まえると、よくいわれる、「基礎から応用へ」という勉強法の真意が見えてきます。まず、問題を読んで何かを思いつく、思い出すための基礎力が必要になります。さらに思いついた解法っぽいものの中から正しいものを組み合わせる応用力が必要になります。基礎力はチャート式のような網羅的な問題集を何周も解き、難しいなら前の問題に立ち返り、問題の意図を理解し道具として扱えるようになることで得られます。応用力は入試レベルの問題を、ただ何となく解くのではなく、基礎の勉強で得た知識をどう組み合わせて解くか考えながら解くことで得られるでしょう。
この、私なりの数学の勉強法が、皆さんの長期的な勉強計画を立てる際に役立てば幸いです。最後になりますが、寒くなり、インフルエンザや風邪が流行りだす季節になりました。皆さんも手洗いうがいを行い、病気には十分ご注意ください。
舩橋先生