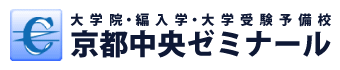突然ですが、皆さんは宗教と言うと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。別に新興宗教の布教ではありませんよ(笑)神や仏を信じる人にとっては自分の人生に必要不可欠なものでしょう。信じない人にとってはあってもなくてもどちらでも良いものでしょう。国際政治やアメリカの政治を学んでいる人にとっては紛争の原因となる厄介なファクターかもしれません。一方で、3.11以後、スピリチュアリティへの関心が高まっているとも言われています。どの立場をとるにせよ、宗教を信じる人々が現代でも存在しており、また宗教が現代の様々な場面で重要な役割果たしているのは確かな事実です。ここに宗教を学問的に研究する必要が出てきます。では、宗教を学問的に研究するとは一体どういうことなのでしょうか。
私は大学でキリスト教の研究をしていますが、キリスト教の場合、伝統的にそれは神学(Theology)が担ってきました。神学は特定の信仰の立場に積極的に関わってキリスト教を研究するものです。信仰が哲学や思想の言葉を借りて自分の姿を表現したものだと言えます。信仰を共有する人には実に生き生きとした信仰の姿を見ることができるでしょう。しかし、主観的過ぎて信仰を共有しない人には意味のない学問かもしれません。
これに対して19世紀に現れたのが宗教学(Science of religion)と呼ばれる立場です。これは宗教に対して外部から客観的に実証主義的にアプローチするものです。キリスト教や仏教や神道といった諸宗教について、その個々の信仰の内容は問うことなく、その信仰対象にはいかなる特徴が共通して存在しているのか、礼拝の仕方にはどういう共通点と相違点があるのか、といった問題を事実に基づいて研究していきます。客観的・実証主義的なので、信仰をもたない人でも理解できますし、面白いと思うこともあるかもしれません。しかし、キリストやブッダや神に共通する特徴を取り出したところで、それは外面的で表面的な話であって本当に宗教の内容を理解したことにはならないと思う人もいます。どちらの方法にも一長一短があるわけです。
ここで私が研究するキリスト教学(Christian studies)が登場します。仏教で言うと、仏教学にあたるものでしょうか。これは神学と宗教学との中間に位置し、神学のように信仰を対象としつつも、自己の信仰という主観に陥ることなく客観的に、しかし宗教学のように表面的な次元に留まることなく、キリスト教を研究する立場です。具体的にいえば、例えばマルティン・ルターといった神学者が残した文献を下にルターが何を言っているのかを客観的に研究することが挙げられます。これは客観性を維持しつつも、プロテスタントのキリスト教の信仰の内容に迫ることができます。そこで得られた成果は、場合によっては、現代の教会やクリスチャンに対して間違っている点を是正するように呼びかけるのに使えるかもしれません。このような学問がキリスト教学です。
もちろん、神学も宗教学も独立の自律した学問であり、その存在意義が消失したというわけではありません。しかし、宗教研究には上記の問題があり、その問題に対する答えのひとつとしてキリスト教学という学問があることは頭の片隅に置いておいてもよいでしょう。
渡部先生