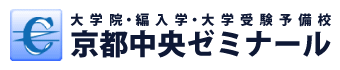私は大学院でHIVをはじめとするウイルスの病原性の研究をしています。学部まで物理化学を専攻しており、生命科学を本格的にはじめたのは大学院に入学してからでした。最も構造がシンプルで生物界の中で特別な立ち位置を占めるウイルスに興味を持ち、現在も多くの人が苦しむエイズウイルスを学ぶことを決意しました。
HIVはエイズ(ヒト免疫不全症候群)を引き起こすウイルスであり、エイズを発症すると免疫力の著しい低下を引き起こし健康な状態ならば感染症を起こさないような病原体にも感染してしまいます。未だ効果的なワクチンは開発されておらず、治療法も確立されていません。HIVは感染するとヒトのゲノム(DNA)のランダムな位置に組み込まれてしまいます。ウイルスが宿主の細胞内に隠れた状態となるので抗ウイルス剤による治療が難しい原因となっています。
人類は過去の長い歴史の中で何回もウイルスの侵入を受けており、我々のDNAの中には過去に侵入したウイルスの由来のDNAが数えきれないほど含まれています(ほとんどがその機能を失っていますが。) ヒトのDNAに侵入したウイルスのうち、HIVのように害を引き起こすウイルスもありましたが、その一方でウイルスが侵入したことでその生物に遺伝的多様性をもたらし、進化に寄与したウイルスもあったでしょう。現在、ヒトがヒトらしい形質をもつことは、過去に多種多様なウイルスがヒトゲノムへの侵入してきた結果だとも言えます。我々の体の細胞に含まれ、日々エネルギーを生み出し続けているミトコンドリアも元々は外来の微生物であったと考えられています。視点を変えてみると次のような考え方もあります。ヒトのゲノムの一部がウイルスとして外界に出ていき(出芽)、その特性を変えて再び元に戻ってくる(感染)。こう考えていくと、ウイルス自体は動物の遺伝子と根本的には同じもののような気がします(やや極端ですが)。
もちろん、HIVのような害のあるウイルス感染を許容しているのではありません。しかし、ウイルスを徹底的に排除、撲滅しようとする治療だけではなく、ウイルスの活性を抑えることで共生する道もあるのではないかと私は考えます。
一瀬先生